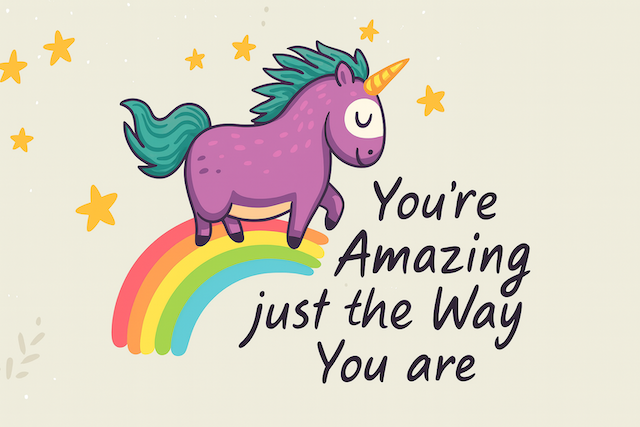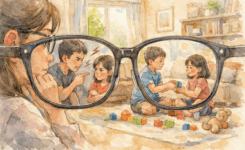「何か有益なことをやるのはよいことだ」という通念が強いと、何もしないことが悪いように感じられることがあります。
無関心、怠惰、無策と見なされるのでは、と不安になるのかもしれません。
人の価値を「何をしているか」で測る傾向が、現代社会には根強くあります。
とくに、身近な人よりも漠然とした「周囲」に対して、SNSを通して活動を示す習慣は、この傾向を強めているようです。
本当は休みたいのに、何かをしている自分を発信するために、さらに行動を重ねてしまうのです。
また、魂や精神性の観点から自分の使命を発揮できる「何か」を求めすぎると、純粋な興味や愉しみが感じられなくなる場合がいるようです。
もちろん、行動が新たな視野や活力を生み出すこともあります。
しかし「行動すること」自体が目的になると、疲弊を招きかねません。
子どもが退屈を持て余すとき、大人が「何をしたらよいかわからない」と悩むとき・・・その背後には、やらなければならないというプレッシャーがあります。
本来、「そのままでよい」「何もしなくてもよい」という選択肢も、等しく大切だと考えられます。
人間関係や仕事でも、余計な心配や気を回しすぎることは少なくありません。
エネルギーが落ちているときほど、自分の感覚が鈍り、不要な努力を重ねてしまいがちです。
先日の下半期リーディングでは、三つのハートセンターを通じて、こうしたテーマが浮かび上がりました。
Sさんの場合。
• ミドル・ハートでは、「私は私でよい」という自己軸の感覚が、大きな癒しとなり、他者に不要に関与しなくなることが示されました。
• ロワー・ハートでは、「むやみに直感的に同調しない」ことが、自分を被害者的な立場に置かないことにつながると気づきました。強い共感力やエンパス体質は無意識の反応ですが、そこに自己満足や代償行為が潜んでいる場合もあります。
• ハイヤー・ハートでは、「自分のエネルギーに集中することが、他者との感情を健全に分かつことにつながる」という真意が現れました。他者に必要以上に同調しようとすると、自分の集中や活力を奪うものになるようです。
とくにハートに関することは、無理にやろうとせず、(ひとまず、やるだけのことをやったなら)成り行きを信頼して安心していると、自然に状況がよい方向へ展開します。
逆に「こうなっては嫌だ」と細かく段取りを作り込むことは、癒しや修復の流れを妨げます。
大切なのは、自然に任せながら「これはやったほうがいい」と感じられる瞬間に動くこと。
そのときは、状況や人の言葉、ひらめきや健全な思考に導かれて、無理なく心地よく行動できます。
そして余計なことをしそうになると、自然にブレーキがかかり「やらなくてもよい」と気づけるようになります。
行動的でつい頑張りすぎる方、あるいは考えすぎて動けなくなる方にとって、「そのままでよい」という選択が、大きな癒しと気づきにつながるでしょう。